不耕起栽培。僕のブログやtwitterをみてくださっている方は1度は聞いたことがある言葉だと思います。反対語は耕起栽培。
wikipediaの概要をみてみると、こんな説明になっています。
農地を耕さないで作物を栽培する、作物の栽培方法の一つ。
-引用元:wikipedia(不耕起栽培)
その通り。超簡単に言ってしまえば土地を耕さずに作物を育てていく栽培方法の事をいいます。
本当に耕さないのか?と言えば、最初の畝だてはしてるよね?って突っ込みどころがあったり、それさえもしないで始めている人もいたり。
僕自身、不耕起栽培を基本として家庭菜園をしています。基本としてって書いたのは、最初の畝だては行っていますし、去年まではジャガイモ栽培するのに耕していたり、つい先日もネギの畝のために鍬をふりました。
でね、今回はどんな話をしていくつもりでいるのかというと、僕が不耕起栽培を選択した理由ですね。
不耕起栽培のメリット・デメリットも含めて、僕が不耕起栽培を選びこだわる理由。そこを書いていきます。
土壌流出を防ぐことができる
僕がまず第1に話たいのがこちら。不耕起栽培をすることで土壌の流出を防ぐことができる。その理由となるポイントは、
- 前作の作物残渣(茎とか葉とか)を地表に放置するので、地表を風雨から守ることができる。
- 耕さないので、草も生えてくることになり土の保持力が高まる。
この2つです。きっとイメージ出来ると思います。耕して土が剥き出しの状態になっているところに雨が降ると表層の土が流されていってしまう。
例えば砂浜で作った山。無防備な状態でそこに雨が降ってきたり、波が押し寄せてきたら、砂は流されていってしまいます。そして、しばらくすれば元通りの平らな砂浜に戻りますよね。耕して、草の生えていない畝というのは、これと同じ状態なんです。
土壌流出=土壌の栄養分の流出
なぜ、土壌流出を防ぎたいのか?という事もお話ししておきます。
土壌流出、それは同時に土壌の栄養分の流出という事になるんですよね。その中でも主に窒素成分は作物の成長に必要な栄養分です。有機肥料や化学肥料として与える事もできますが、不耕起の自然栽培においては作物残渣や刈った草がそれに当たります。
土壌微生物やミミズなどの土壌生物が作物残渣や刈った草という有機物を分解し、植物が吸収できる無機物の形にしてくれます。
なので、耕すことはせずに育てていた作物の葉や茎、刈り取った草、それらを畝に被せておくことは土壌を守るバリアの役割も持ちつつ、土を豊かにする素材にもなっています。
全てを説明はできていませんが、土を耕さないことで作物にとって良いサイクルが回り始めるのが伝わっていると嬉しいです。

落ち葉の堆肥
土壌生物、微生物の多様化と土壌環境の改善
不耕起栽培をすることは作物にとって良い流れを生みはじめます。そして、それを助けている土壌生物、土壌微生物にとっても同じことが言えます。
単純明快な1つの例としては、鍬で土を耕すと間違いなくミミズを殺してしまいます。鍬ならまだカワイイものですが、耕運機を使ったらどうなるだろう…想像するまでもないですよね。ミミズは土壌環境を作っていく重要な分解者です。
その他にもカビや目に見えない微生物たちもミミズ同様に重要な役割を担っています。
耕さないことで草が生えます、その根の周りには微生物が集まります。畝の上に重ねられている残渣や枯れ草にはカビが繁殖します。
残渣や草といった有機物はミミズや微生物などの土壌生物が食して排泄する事よって分解され、彼らの排泄物や生成物によって土の団粒化が進みます。
それは、作物の生育しやすい豊かな土壌が作られていく事を意味しています。
生物の多様性が増すことでバランスが整う
こうして土壌環境が整っていくということと同時に、様々な草が育つことで生活する昆虫たちも多様化していきます。
土壌生物、土壌微生物、菌、昆虫の多様化が進む事で、病原菌や害虫の繁殖も抑えます。共生することで特定の生き物が大繁殖をする事を避けられているんですね。
僕の畑は草だらけなのですが、虫による食害って実際に少ないです。
…と言いつつ、春先にはモンシロチョウの幼虫などにアブラナ科の作物を食い荒らされる…という事は起こっていますが(笑)
草への応じ方、見極めには経験が必要
不耕起栽培を行うことで、草との共生という道を歩む事になります。
デメリットというか、1つ感じることは草への応じ方は実地で経験していくしか身につかないという事ですね。その中でも参考にできる参考書はあります。例えば、
実際に僕も教科書のように読ませていただいています。
技術的な事や見るべきポイント、考え方は学べます。ですが、実際に自分の畑を見ているのは自分だけなんですよね。
その土地、その地域の気候や土壌を実際に感じるのは自分自身です。隣の地域へ行けば、土壌も変わります。生えている草の種類だって違います。そうした中で、いかにして書いてきたような環境に整えていくか?
僕自身、まだまだ経験が足りていませんし、見えていないことがたくさんあります。正直、これまでの数年間は作物を育てていたのか草を育てていたのかわからなくなる時期もありました。
畑を始めて5年目、やっと満足のいく収穫があったり、元気に育ってくれているなぁという実感を持てたりし始めています。

籾殻の燻炭
理にかなっているから選んだ不耕起栽培
先ほども書いたように上手くいかない時期がしばらくあったんですよね。そんな時に、それでも不耕起栽培だと、不耕起栽培にして自然栽培を実現させたいと強く思わせてくれた書籍があります。
海外での不耕起栽培の話が取り上げられています。日本の状況とは違いますが、とても勇気が湧いてくる1冊になっています。
不耕起栽培にすることで、肥料や農薬に頼らないサイクルが生まれます。とても理にかなっているんですよ。不耕起栽培や自然栽培って魔法でもなんでもなくて、実は徹頭徹尾、「理」なんですよね。
確かに最初からうまくいくとは限らないです。でも、『理にかなっている』から始めていかなければ。1つ1つ経験しながらクリアしていけば近づいていける。そう言う確信を感じられる。
小さな不耕起、自然栽培者が増えてほしい
僕は日本の農家の方々に『不耕起栽培にしろー!』とか、農薬は絶対に使うなとか、化学肥料もダメだなんて微塵も言う気がないです。小さな家庭菜園ですけど、めちゃくちゃ大変なんですよね。何も使わないのは。サイクルが回り始めれば少しは楽になると思うけど。
今現在の外食産業、流通システム、消費の形で暮らしていくとなると無理なんですよね。きっと。変えるべきは農家さんではなく、システムの方だと思います。構造の問題。
で、僕が始めたのはそう言うシステムや構造の外側に出て、やれる事をやると言う話なんですよね。
全てを自給自足で生きていくのは難しい。色々と考えますが、街に働きに出ながらってけっこう苦しい気がしている。
でも、興味や関心がある個人個人が少しずつでも変わっていく事に意味はあると僕は思っているんですよね。大局的にはシステムを変えなければ変わらない。でも、小さな地域ごとでも始める人が増えていけば、その地域では新たなサイクルが回るとおもっている。
だんだん、熱くなってきてしまったけど、今回はこの辺りまでにしますね。ご意見や一緒に畑したい!と言う方、いらっしゃれば気軽にメッセージしてくださいね!ではでは。





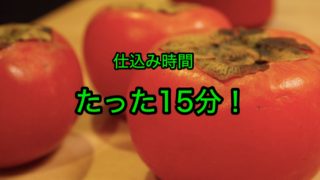










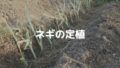

コメント